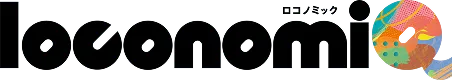「私たちは弁当を売っているのではなく、旅の思い出を提供している。」
そう話すのは群馬県・横川の老舗・荻野屋を率いる6代目、高見澤志和社長。旅の楽しみは、目的地に着くことだけではない。道中の風景や会話、そして食事。その全てが重なり合い、一つの「記憶」となるという。
かつて難所と呼ばれた碓氷峠の麓で、140年にわたり旅人の腹と心を満たしてきた。1958年に看板商品の峠の釜めしを筆頭に、伝統の味を守りながら、アニメコラボや都心への新業態出店など、矢継ぎ早に革新を仕掛けている。単なる事業拡大ではなく、峠の釜めしを旅の記憶装置へと昇華させる高見澤氏の壮大なブランド戦略について伺った。

1984年北海道札幌市生まれ。2007年に株式会社オプトへ入社し、ソウルドアウト創業に参画。営業領域の責任者として全国の中小・ベンチャー企業支援を拡大し、ソウルドアウトの東証マザーズおよび東証一部上場に貢献。その後、CROやマーケティングカンパニープレジデントを歴任し、2024年より専務取締役COOに就任。
現在は「ローカル×AIファースト」戦略のもと、全国拠点展開とデジタル活用を通じて地域企業の成長を後押しし、日本経済の持続的な活性化に取り組む。

目次
峠の釜めしがプロダクトとして最大化する旅の体験価値と思い出

まず、荻野屋の原点である「お客様に喜んでいただきたい」という信念に対して、高見澤社長はどのように解釈されていて、経営理念として継承されているか教えてください。
当然ながら、私達は長年にわたりお客様あっての商売としてやってきました。
「感謝、和顔(わげん)、誠実」が、社是としてお客様に向き合う姿勢にあり、なによりも「お客様に喜んでいただく」ことをテーマに事業をしています。
私達の原点は温泉旅館にありますが、創業以来、旅のお客様がメインでした。旅はレジャー・娯楽のひとつとして、楽しみにしている方がとても多いものです。その旅を支える私たちが、義務的な仕事をするだけではいけない。時代は変わっても「おもてなし」や「真心」を込めるという軸は普遍的です。
かつて冷えた幕の内弁当が常識だった時代に「温かい弁当を提供すること」が、お客様に喜んでいただくための表現方法のひとつだったように、現代のお客様の課題や困りごとをきちんと把握した上で、旅の楽しさや思い出づくりのために何ができるかを意識しています。
峠の釜めしという強力なプロダクトがあると「いかに美味しく提供するか」の方向に考えがちだと思うのですが、「旅の体験価値を最大化する」方向に考えるのは昔から受け継がれてきた形なのでしょうか。
過去の代表がどう考えていたかまでは、正直なところ私にはわかりませんが、経営を引き継いでからこれまでを振り返ってみると、「旅の体験価値を最大化する」といった視点は非常に重要だと感じています。お客様に喜んでいただくということは、先代以前より言われてきたことですが、思いが一緒だとしても、手段は時代に合わせて変えていくべきでしょう。
お客様が口にする峠の釜めしを美味しく提供するのは、ある意味当たり前のことで、お金をいただいている以上、美味しさに対する妥協は一切ありません。その上で、どうすればお客様の旅の楽しさや思い出づくりに貢献できるのか。その視点を大切にしています。

変化が激しいこの時代において、どのような方法で顧客のニーズを探られているのか教えてください。
自分が旅をした時に「こうなったら良いのに」「こうだったら楽しく過ごせる」と感じた経験がなければ、なかなか顧客のニーズに気づけないことも多いです。だからこそ、自分自身がお客様の立場として積極的に情報を取りに行ったり自ら体験しに行ったりすることが、重要な方法だと考えています。
加えて、外部のメディアを含め、世の中のさまざまな情報に触れておくことも意識しています。
そうしないと、顧客のニーズに気づけなくなったり、経営者としての感覚が鈍くなってしまうという危機感を常に持っています。事業には直接関係のないトレンドであっても、世の中で何が流行しているのかという視点を常に持ち、時間の許す限り情報収集に務めています。
一方で、運営されている飲食店の全てのメニューをチェックしているなど、抜かりのなさにはギャップも感じますね。
そもそも、飲食店は「美味しい」から何度も利用してくださるお客様がいらっしゃると思うのです。峠の釜めしに関して言えば、独特の釜容器が記憶に結びつくことで、それを思い出し再購入のサイクルが生まれた側面もありますが、結局のところ「美味しい」と感じてもらえなければ、再購入はありません。「美味しいかどうか」は、飲食事業において非常に重要だと考えています。
もちろん美味しさは主観によるところが大きいので、すべてのお客様にご満足いただくのは難しいかもしれません。それでも最低限、自分自身が美味しいと思えるものを提供する。そのために自社で販売しているものに関して、できる限り全て味見をすることは、私にとってはごく当たり前のことです。
挑戦の一歩を踏み出し続けてきたからこそ未来を作れた

創業から140年、長く社会から必要とされ続けるってすごいことだと思うのですが、経営理念やパーパスについて、日々の意思決定や社員の行動にはどのような形で落とし込まれているのでしょうか。
どこまで落とし込めているのか不安もありつつですが、やはり、繰り返し言い続けることが大切だと思います。荻野屋のミッションは「思い出作りのお手伝い」ですが、私たちの仕事はサービス業として旅館業から始まっており、旅に来たお客様にとって休憩や宿泊の場は、記憶に結びつく重要な場所を運営してきました。私たちの仕事は、お客様がまさにその記憶として、思い出をつくることだと考えています。
お客様の荻野屋の利用は、一期一会の機会かもしれません。しかし、お客様の人生という長い時間で考えれば、その一瞬も非常に大切な時間です。二度と来ないかもしれないからといって、適当な仕事をしてはいけない。また来た時に、「あの時良かったよね」という思いを残せるよう、真摯に向き合わなければならない。その気持ちで日々仕事をするのだと伝えています。
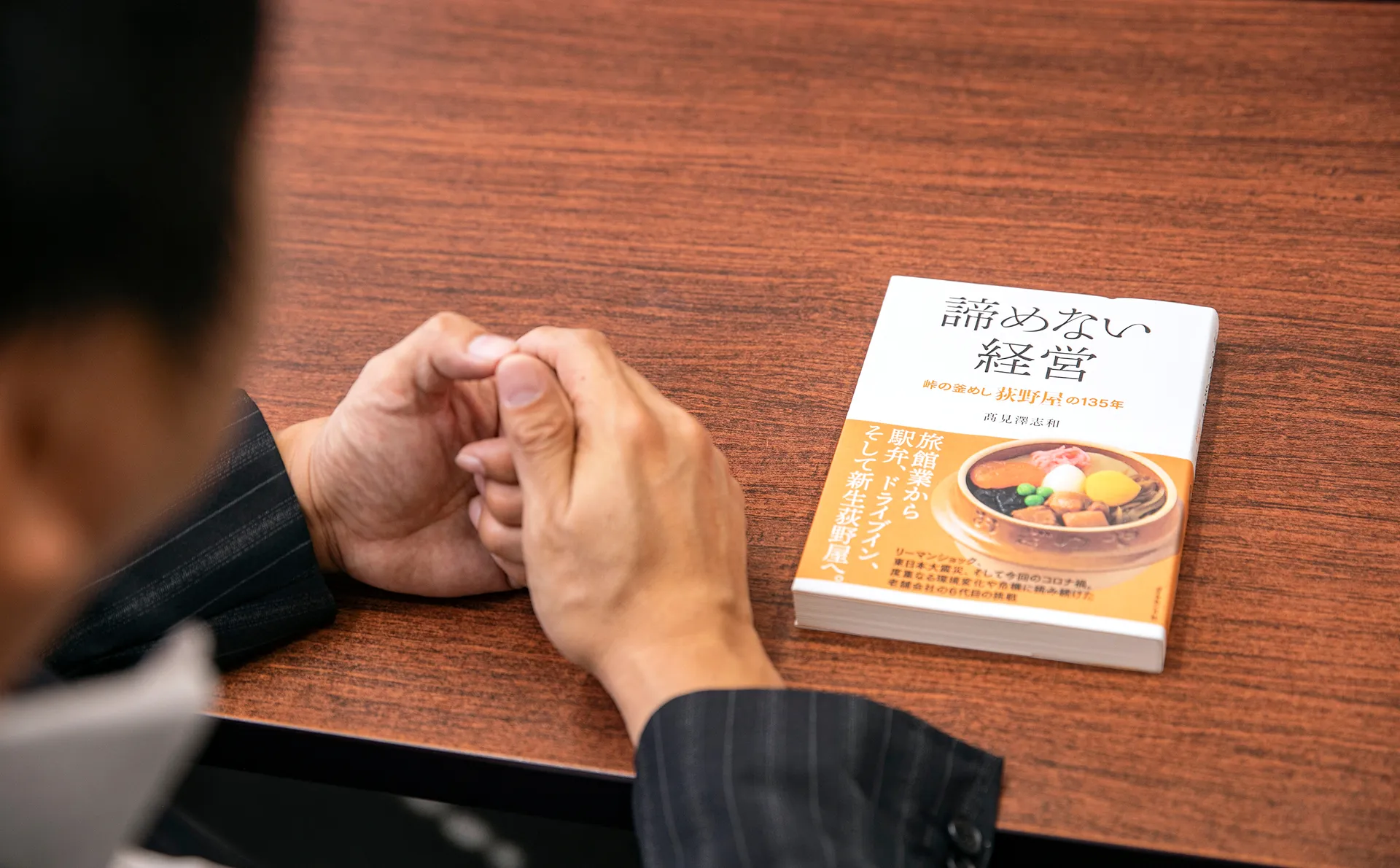
著書「諦めない経営」の中でも、飽きられないように挑戦を続けていく姿勢を大切にされているとありましたが、そういった姿勢が荻野屋の精神として受け継がれているのですね。
創業から140年という歳月は結果としてあるものですが、最初はゼロからのスタートです。誰もがそうですが、その一歩を踏み出すことがなければ何も続きません。安定だけを求めていたら時代に取り残され、長く続かないのです。
140年前に私の祖先が新しいチャレンジをした事実があるから、その挑戦の精神は今も変わらないはずだと考えています。振り返れば、時代の節目節目でさまざまな困難がありましたが、その都度、挑戦の一歩を踏み出し続けてきたからこそ未来が作られてきました。
会社の歴史そのものが、挑戦し続ける必要性を証明する良い教科書なのです。だからこそ、常にチャレンジしていく姿勢を大切にしています。
人生の土台を形成した荻野屋を継承することで果たす責任

「家業を継ぐつもりはなかった」状況から一転、当時生活していたロンドンから帰国して6代目として重責を担うまでの経緯について、「長男として家に戻るのが責務」だと感じられたとのことですが、きっかけがあったのでしょうか。
長男だから継がなくてはならないという発想は、特にありませんでした。ただ、「長男が家業を継承する」という仕組みに、現代の日本を築いてきた側面があるならば、その責務に倣うべきではないかと感じたのです。
何よりも、生まれてからずっと荻野屋という会社に支えられ、育ててもらったという思いが根底にあります。さまざまな葛藤はありましたが、良くも悪くも、この会社があったからこそ今の自分がある。長年、会社に対して借りを作ってきたような感覚がありました。
当時、さまざまな事情が重なって、比較的どんどんと話が進んでいったような形だったと思うのですが、もし何も起きていなければまったく別の人生を歩まれていたでしょうか。
父と反りが合わなかったこともあり、何もなければ家に戻らないまま別の道を歩んでいた可能性は高いと感じています。実際、周囲には似たような環境で家業に戻る友人もいましたが、自分はそうならないだろうと思っていました。
しかし、私がロンドンへ行くにしても、学費を含めて荻野屋から恩恵を受けていました。荻野屋があり、両親からの支援を受けることができた。自分が生きてきた土台は、自分の力ではなく荻野屋が作ったものといってもいい。家業への反発心もありましたが、いざ会社が大変な状況に直面した時、存続させる責任を果たす形で借りを返すことが、私に残された道だと腹を括ることができたのだと思います。
社長に就任した当時、「利益に対する意識」を根付かせたとお伺いしましたが、伝統的な組織に「仕組み化」「標準化」という合理性を導入するにあたって、社員のみなさんからの抵抗は強かったですか。
やはり、いきなり考え方を変えることに対する反発はありました。いまでもゼロではないと思います。二十代半ばの若者がいきなり来て偉そうに言っても、誰も言うことなんて聞かないですよ。
しかしながら、会社が立ち行かなくなったらこれまで当たり前にもらえていた給料はどうするのかという現実的な問題もあります。会社が未来永劫続いていくための責務として、合理性の導入について必要性を理解してもらうため、役員から順に、そして最終的には一人ひとりと時間をかけてじっくりと話をして納得してもらうことに努めました。そうして、徐々に意識を変えていってもらいました。

当初から、社長の考えに共感や賛同してくれた方もいらっしゃったのでしょうか。
少なからず賛同してくれる人がいてくれたからこそ、進められたのだと思います。人数よりもキーパーソンが、私の考えを全面的に支持してくれたのが非常に大きかった。ある意味、政治的な側面もあったのかもしれませんが、持ちつ持たれつの発想でやっていましたね。
私にとっては、今までそれほど交流のなかった方々がいきなり部下になったわけです。事業承継の準備を進められていなかったことも相まってハードな状況でしたが、「次の代が変わったら、それに従う」というDNAを社員のみなさんがどこかで持っていてくれたのかもしれません。それも、スムーズに進められた一つの要因だったと感じています。
コト商品としての合理性と認知拡大 両輪で目指す事業成長

峠の釜めしを「モノ」ではなく、思い出づくりをお手伝いする「コト」商品として捉える考え方について、ローカルに根付かせて事業成長させていく上で合理性を感じる場面はありますか。
最初はそこまで深く考えていませんでしたが、事業を進めるほどに、峠の釜めしという商品が、単なる商品ではないと実感します。
多くの方が、旅の行き先や一緒に行った人などの思い出と結びつけて語ってくれる。ある意味、このローカルな地で峠の釜めしを食べることが、お客様と地域との大切な接点になっているのです。
観光の視点から見ると、私どもの商品を通じて地域がより目的地化します。実際、当時は峠の釜めしが目的地のひとつになっていた側面もありました。そのように考えると、「コト」商品としての発想は、地域に根差して事業を成長させていく上で、非常に合理的だと感じています。
それでは、これからも基本的にはローカルの地を大切にしながら事業を推進されていくのでしょうか。
それはローカルの捉え方によると思っています。現在、東京に拠点を出しているのはマーケットの大きさもさることながら、知ってもらう機会を広げるための重要なタッチポイントだと考えるからです。
国際化が進む中で、知られていなければ事業は伸びません。だからこそ、より多くの方に知ってもらうために、積極的に活動していく必要があります。
一方で、やはりこの地元に来て食べていただくということも重要です。先代は「わざわざ来てもらうからこそ価値がある」という考えでしたが、やはりそれだけではだめなのです。地元を大切にすることと、都市部で認知を拡大すること、この両輪をいかに効率良く回していくかが、これからの重要なテーマだと認識しています。
広がり続ける荻野屋ブランド、変革の原動力はお客様の声

ライトノベルやアニメなどIP(知的財産)とのコラボレーションを積極的に展開している目的について、「タッチポイントを増やし、認知度を上げる」こと以外に、伝統的な駅弁ブランドのイメージを、現代の若者や新しい顧客層に対してどのようにリブランディングしたい意図がありますか。
最初は認知してもらうためのタッチポイントの創出からスタートしました。ライトノベルとのコラボレーションは、たまたまこの地域が舞台になっている作品を見つけたのがきっかけです。
伝統的なブランドでも、忘れ去られたり知られていなかったりすれば来てもらえない。それなら荻野屋を知らなくてもそのIPを知っていれば、そこから新しい接点を持てるのではないかというのが最初のテーマでした。
駅弁や峠の釜めしは伝統的なものである一方で、若者から見れば少し古いものだといった感覚もあると思いますが、そもそも高見澤社長はそういうイメージを変えていきたいとお考えなのでしょうか。
古いイメージを変えていきたいとは考えていないかもしれません。伝統なんて最初はゼロだったわけですから。たまたま続いているから「伝統」と呼ばれるという感覚です。
例えば、今取り組んでいるIPコラボが100年続いたとすれば、それはまた伝統だと言われるでしょう。そうだとするなら、成功するかどうか分からないのであれば、まずはやってみようというスタンスです。伝統とは、新しい挑戦を続けた結果として自然に作られていくものではないでしょうか。良ければ世の中に残っていくし、そうでなければ廃れていくだけだと考えています。
若者、女性など顧客層を絞るのではなく、あくまでも自分達がやるべきことの追求を続けた結果、それが受け入れられれば残るということですね。
すでに多様なファンがいるIPとのコラボレーションによって、新しい顧客層へアピールできますし、既存のファンの方々にもIPを知ってもらう機会になる。そんなwin-winの関係を作れると考えていますので、今後もアニメやキャラクターだけに留まることなく、幅広く積極的にコラボレーションしていきたいですね。
実はもうひとつ、外部の文化を取り入れることは多様性を学び、イノベーションにつながる機会になるため、社内にも良い影響があります。確証はありませんが、これまで自分たちのことしかやってこなかった組織が挑戦し続けることで、何らかの経験値が得られるはずだと考えています。

新業態『荻野屋 回 -kai-』を都心の激戦区に出店する戦略的意義について、「市場の分散化」や「収益の多様化」以外に、「荻野屋」というブランドとしてどのような変化を期待されていますか?
私たちには「峠の釜めし」という圧倒的に強い商品があります。これは非常にありがたいことですが、一方で「これしかやっていない」と見られてしまうことが長年の課題でもありました。 社内を見渡せば、実はさまざまなリソースやサービスが存在しています。それらを切り出し、単体でも勝負できるのではないか。特に飲食業態であれば、これまでの実績を活かしてスピンオフが可能だと考えました。
「峠の釜めし以外に柱を作る」。これが今、私たちが挑戦しているテーマの一つです。今後もこの挑戦は続けていきますが、やり方は柔軟に変えながら、荻野屋というブランドの可能性を広げていきたいと考えています。
新業態のコンセプト「伝統の出汁を進化させる」にあるように、伝統の核を「釜容器」から「中身」へと切り替えているようにお見受けしますが、伝統の継承と革新の境界線をどこに引いていますか?
「峠の釜めし」という商品を分解していくと、弁当であり、食事であり、原材料や9種類の具材、そして釜容器といった要素が出てきます。完成品としては1つですが、分解すればさまざまな枝分かれが可能になります。そこから別の形で作れるのではないか、せっかくのノウハウを峠の釜めしのためだけに留めておくのはもったいないだろうという発想です。
「守るべきもの」と「変えていいもの」の境界線。究極的には「自分がいいと思うか、好きかどうか」という直感的な部分もありますが、基本的には「クオリティ」と「お客様が本当に求めているか」を判断基準にしています。
例えば、パルプモールド容器の導入についても賛否両論ありました。「思い出を壊すな」というお叱りの声もいただきましたが、一方で「重くて持ち帰れない」「陶器の処理に困る」というお客様の声も以前から多く届いていたのです。
「峠の釜めし」がお客様の声から生まれたのであれば、それを変えるのもまた、お客様の声でなければならない。そう考え、空弁(機内食)への展開というタイミングも重なり、軽量タイプの容器も導入する容器の変更という決断に至りました。
100億円企業へ 規模の追求と人への投資

創業140周年を迎えられて、将来のビジョンについて売上規模を追求していくことに対するスタンスとあわせてお聞かせください。
未来永劫続いていくことがビジョンであり、峠の釜めしだけでなく、さまざまな軸ができてくることを目指しています。規模の追求については、会社としても経営者としても必要であり、実際に目指しているところです。
ただし、市場のニーズとマッチしなければ売上は上がりません。例えば100億円を目指すのであれば、それにつながる「武器」を持ち続けなければなりません。飲食や食品製造を軸としつつ、それらとシナジーのある事業を組み合わせながら、規模を追求していきたいと考えています。
その実現に向けた課題、特に組織や人材面での不足についてはどう感じていますか?
一番の課題は「人」です。現状の事業を回す力はありますが、新しいものを形にして独り立ちさせていく人材が圧倒的に足りません。既存事業の方が楽で成功体験もあるため、どうしても思考がそちらに流れてしまいがちです。 新しいこと、なかなか芽が出ないことにもへこたれずに一緒に作り上げていく人材や、それを確保する社内インフラが必要です。
自社にないものをゼロから作るのは難しいため、外部のノウハウを取り込んだり、積極的に組んだりすることも必要だと考えています。雇用形態にはこだわらず、実績を残して一生一緒にやるという気概のある方と組みたいですね。

事業上の課題として、地域の人口減少などについてはどうお考えですか?荻野屋がリーダーシップをとって、地域を目的地化していく構想はあるのでしょうか。
横川地区の人口減少は避けられない課題です。本来は行政の仕事かもしれませんが、会社が力を持って「このエリアに住みたい」「この会社で働きたい」と思わせるような魅力作りが必要です。
私たちも、この地域を目的地化したいと強く思っています。都心に住む優秀な人たちが、企業の「Will(意志)」に反応して力を貸してくれるようになれば面白い。 横川という通過点的な場所を目的地化できれば、ビジネスをする人が増え、居住者が増え、生活インフラが整うという循環が生まれるはずです。軽井沢や御代田のように、優秀な若者が移住してくる可能性は十分にあります。ここも自然が豊かでアクセスも良いので、ポテンシャルはあると信じています。
海外への展開についてはどうお考えですか?
以前は考えていましたが、まずは足元を固めることが重要だと考えています。海外で何度か挑戦してわかったのは、「日本で通用するからといって海外で通用するわけではない」ということです。まずはインバウンドの方々に知っていただき、食べていただくことから始めたいと考えています。
本日はありがとうございました。


北川 共史 TOMOFUMI KITAGAWA
編集後記
今回の取材から見えてきたのは、「旅の価値の最大化」という理念の裏にある、高見澤社長の徹底したリアリズムです。高見澤社長はまずビジネスとして成功し、経済的な裏付けを持つことこそが地域と従業員を守る唯一の道だと断じます。
このシビアな経営観は、家業を継ぐ中で「長年、会社に対して借りを作ってきた」という意識と、会社存続への責務感から生まれた覚悟から育まれていました。
「温かく美味しい釜めしこそが価値」という信念があった中でも、例えば容器の変更など守りなき決断を推進できたのは、「お客様が本当に求めているか」という判断基準に徹した論理的帰結であると感じました。
伝統を「新しい挑戦の結果」と捉えるスタンスで、新業態(釜めし以外に柱を作る)やIPコラボを通じてブランドの可能性を広げ続けるその姿は、140年の重責を背負いながら、未来永劫続く企業を目指すリーダーの挑戦の精神を体現されています。