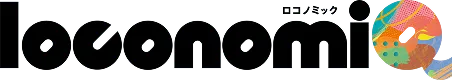「この美しい珠洲の景観を、変わらないまま次の世代へつなげていきたい」
そう語るのは、株式会社NAIAで代表を務める清水 雅楽乃さん。アステナホールディングス株式会社の管理本部副部長として、グループ全体の業務効率化に従事していたが、2021年、石川県珠洲市への本社機能移転時に新規事業推進室へ。現在は能登地方の産業と連携しながら、スキンケア製品を製造・販売している。
本記事では、事業を通じて地域循環の実現を目指す清水さんに、ブランド立ち上げの経緯やリリース間際に襲った震災からの再起、そしてブランドの将来について話を伺った。

1984年北海道札幌市生まれ。2007年に株式会社オプトへ入社し、ソウルドアウト創業に参画。営業領域の責任者として全国の中小・ベンチャー企業支援を拡大し、ソウルドアウトの東証マザーズおよび東証一部上場に貢献。その後、CROやマーケティングカンパニープレジデントを歴任し、2024年より専務取締役COOに就任。
現在は「ローカル×AIファースト」戦略のもと、全国拠点展開とデジタル活用を通じて地域企業の成長を後押しし、日本経済の持続的な活性化に取り組む。
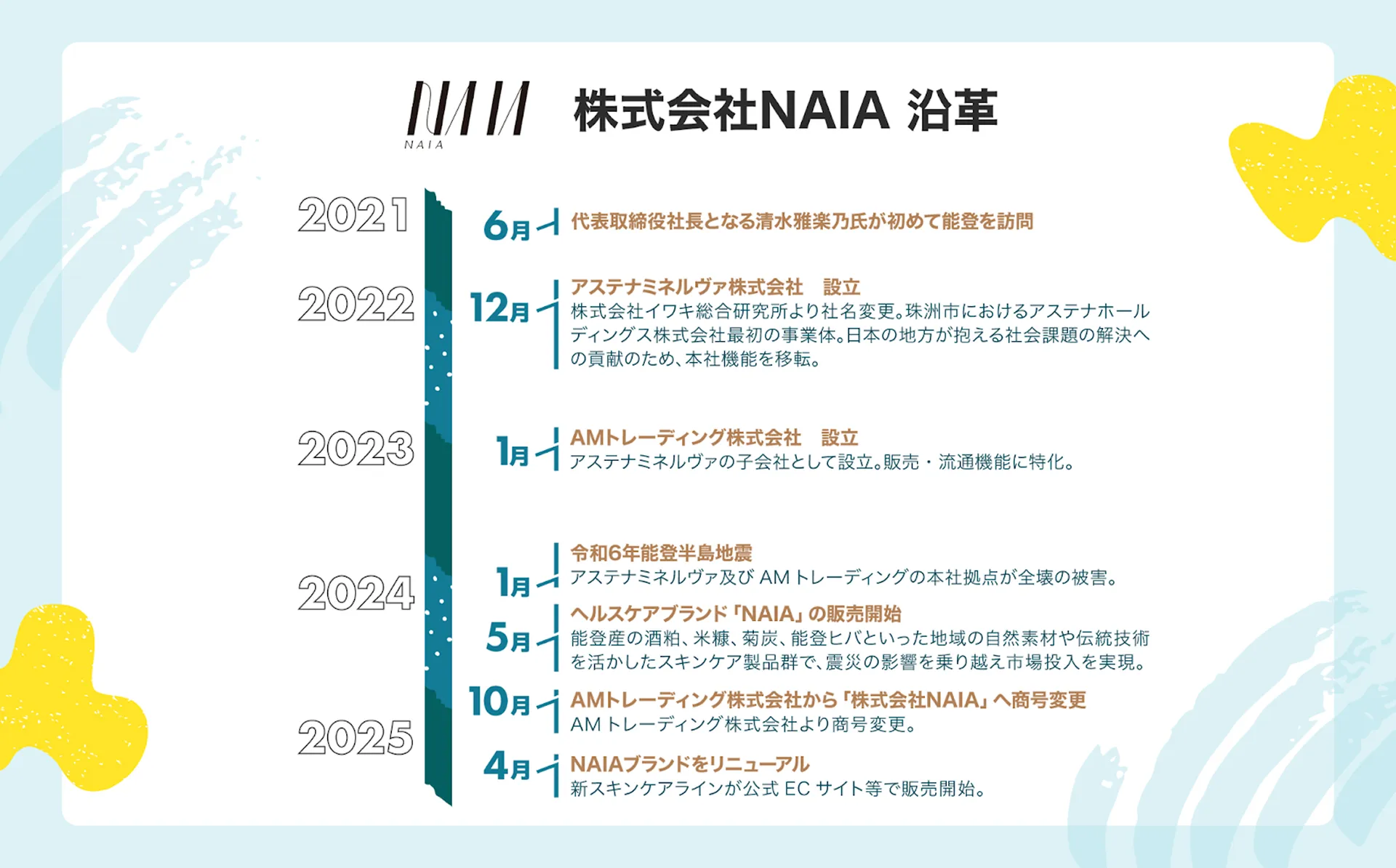
目次
能登地方・珠洲市へ本社機能の移転とまったく新しい事業への不安

まず、能登へ本社機能を移転して新規事業を推進する役割を引き受けた際のお気持ちや、立ち上げ時のメンバー構成について教えてください。
本社機能の一部を珠洲に移転すると聞いたとき、私を含め、社員全員が非常に驚きました。
私がプロジェクトの担当に決まったのは、2021年6月の本社機能移転とほぼ同時期でした。ゼロからの構築になるとわかっていたからこそ、自分に務まるのかという不安な気持ちが大きかったように思います。
立ち上げ当初は7名のチームで、本社管理部門担当が5名、新規事業担当が私を含めて専任2名という体制。私自身は出張ベースでの関与でしたが、チームのほとんどのメンバーは珠洲に移住。現地に身を置いて地域の方々と接点をつくり、地域を深く知ることから始めました。

移転当初、現地に足を運ばれた際に印象に残っているものがあれば教えてください。
初めて珠洲を訪れたとき、一番印象に残ったのは風景の美しさでした。空路で能登空港から車で珠洲へ移動する道中、山々や家並みに自然と目を奪われました。
特に心にとまっているのは、海沿いの田んぼの風景です。緑の水田と青い海、そして空の青さが一体となった本当に美しい景観でした。訪れたのが6月だったこともあり、自然の色彩がいっそう鮮やかに映りました。
珠洲で暮らす人の感性にも影響を与えているはずの風景や気候、その空気を肌で体感できたことは、私にとって大きな収穫となりました。
劇的なソリューションを期待されているように感じた重圧

そんな場所で新しい事業をつくるにあたって、最初の一歩は順調に滑り出したのでしょうか。
立ち上げ初期は、“事業をつくる”より“まずは地域の困りごとに応える”というスタンスで動き、それが後にビジネスへと発展していきました。最初から利益やスケールを追うのではなく、「役に立つ」ことに真っすぐ向き合う。その姿勢が、立ち上げ初期を支えた大きな軸でした。
珠洲には、病院が遠くて高齢者の通院が難しかったり、進学先の選択肢が限られていたりといった明確な課題はありましたが、地域の方々に話を聞いても困っているようには捉えていませんでした。
都会では日常的にさまざまなサービスを受けることが当たり前になっていますが、珠洲ではそういった感覚がないように思えました。だからこそ、本質的なニーズを掘り起こすには対話を重ね、生活の中に入り込んでいく必要があると強く実感したのです。
現地で一緒に住んでみて、本質的な課題や構造を捉えながら事業をつくっていくというのは簡単ではないですよね。
当初はドローンで物流を支える仕組みや自動運転の導入、アプリによる生活インフラの高度化などの事業で成功モデルをつくることができれば、それを高齢化が進む他地域や海外へ横展開できるのではないか、という期待もあったように思います。
しかし、地域の方々と向き合ってみると、テクノロジーを活用した事業は規模が大きすぎて、私たちの手に負えない現実に直面しました。県外からスタートアップ企業を招いてサービスを提供できたとしても、それが土地に根づくのか?という疑問は拭いきれませんでした。
何よりも重要なのは「本当に人の役に立つのか?」という視点です。目新しさや規模感にとらわれず、地域の課題をきちんと理解し、現実的な解決策を見いだしていく姿勢が何よりも求められると痛感しました。
“変わらない珠洲へ” 一次産業の価値をアップデートして次世代に残したい

期待値のコントロールもすごく難しかったと思うのですが、どのように合意点を見いだしたのでしょうか。
地域の方々と話して見えてきたのは、農業でいえば事業承継が進まない、高齢化で担い手が減っている、価格が上がらず生計が立てづらいなど、生活に根ざした身近な課題でした。
農業従事者の平均年齢は70歳近く。日本酒を造る職人や古くからある炭焼き職人も同様で、一次産業全体に共通する課題でもありました。耕作放棄地が増えれば、日本らしい景観や文化の維持も難しくなるでしょう。
大きな「地方創生」よりも、目に見えやすい課題に向き合い、地に足のついたものづくりの方が現実的なのではないか。合意点を見いだすには理想を語るよりも、実際に何に困っているのかを一緒に発見し、小さな成功体験を共有していくことが大切だったのです。
「清水さんは珠洲をどうしたいんですか?」
事業のアイデア探しに奔走し方向性が見えなくなっていたある日、地元の方から問われた一言です。これが大きな転機となり「今のままの珠洲の美しさを、次世代へつなげたい」というコンセプトにたどり着きました。

地域の一次産業が抱える課題を解決するために行き着いたのが「ものづくり」だった。
一次産業の課題解決、その本質は「売れる仕組みをつくること」だと気づきました。どれだけ意義があっても、売れなければ続けられません。
能登地方では、多くの方々が年金を主な収入源にしています。
ここに産業を通じて外からお金が入ってくる構造ができれば、循環が生まれるだけでなく、現役世代が豊かに働ける環境づくりにつながります。一次産業の価値を持続可能にするには、現代のニーズに合わせて形を変えていく必要があるのです。これは能登に限らず、日本各地で共通する課題です。
地域の産業に新しい価値を加え、その土地の課題に向き合うことで持続可能なモデルをつくる。それが「残す」ということであり「次世代へつなぐ」ことだと定義しました。
そして、一次産業の現場や職人の手仕事とつながることに注力しました。
適正価格で原材料を仕入れ生産者を支えるフェアトレード的な価値観を込め、品質だけでなく、背景にあるプロセスを含めた「誠実なものづくり」を貫くこと。それがブランドの根幹となり、独自性にもつながったと考えています。
地元事業者との連携によってもたらされる “NAIAらしさ”

原材料の「酒かす」「菊炭」など、まさに能登・珠洲の土地でなければ作れないと感じますが、開発当初、酒蔵さんや製炭工場の方とはどのような連携をされていたのでしょうか。
たとえば、酒かすを提供いただいた櫻田酒造さんには、あるとき、彼らが通常使う酒米とは異なるお米で「お酒を造ってもらえませんか」と相談したことがあります。
香味や発酵のプロセスなど、正直わからないことも多かったので、手間のかかる試みだったと思います。しかも当時は、酒造りをほぼ一人でこなしておられたので、新しい酒米にチャレンジする余裕なんて、本来あまりなかったはずなんです。それでも快く「やってみましょう」と引き受けてくださって、本当にありがたかったです。
少子高齢化や人口減少という構造的問題が確実に進行している一方で、土地への深い愛着や責任感から「何とかしないと」という思いは皆さんに共通しています。そうした中で私たちは「一緒にやりましょう」という姿勢を大切にしてきました。
珠洲市や能登地方の方々と事業を通じて接する中で、ご自身の中に新しく生まれた価値観があれば教えてください。
地域の方々と接する中で印象的なのは、淡々と日々の営みに向き合う皆さんの姿です。
職人として自分の仕事を黙々と続け、ブレることなく地に足がついている。そんな姿に深い感銘を受けました。
都市部ではどうしても「新しいことに飛びつかなければ」「期待に応えなければ」というプレッシャーがつきまといますが、こちらではそういった焦りや打算のようなものが見られません。それぞれが自分の世界観を持ち、他人と比較せずに生きているのだと思います。

「能登(Noto)、自然(Natural)、職人技(Artisanship)、循環(Inclusive)、本物(Authentic)から成る「NAIA」ですが、ブランド名を決めるまでのエピソードについて教えてください。
私たちが目指したのは一過性で消費されるものではなく、日常に自然となじみ、心と体に作用する存在です。使い手の生活に、能登の癒しや神秘性が溶け込む体験を生み出すことが“ブランドの本質”だと考えました。
職人の技術や、自然と共にある暮らし、そしてこの地域に根付く文化の奥深さと神秘性。実際に住んでみて感じた能登の価値を、ブランド名として言語化したいと考えていました。米づくりが風景の維持につながり、炭焼きが森の循環を支える。こうした営みがつながっている実感を一つの価値として表現しています。
「Authentic=本物」には、地域の職人が魂を込めて作るものを誠実に表現する姿勢や、マーケティングとものづくりの両方を本気で追求する決意を込めています。素晴らしい技術や素材を“ブランド”として昇華させるため、単なる地域活性ではなく、持続的なビジネスとして価値を創出していきたい。それが「NAIA」に込めた思いです。
能登半島地震の影響と再起に向けた歩み

2年ほどかけて準備を進め、リリースしようとした矢先の震災被害だったかと思いますが、率直に当時のお気持ちや頭に浮かんだ言葉、感情を伺えますか。
正直なところ、なんとも表現し難い感情でした。まず何よりも先に、プロジェクトを通じて関わってきた地域の方々の顔が浮かび、雇用していたスタッフやその家族の安否が頭をよぎりました。
事業の性質上、文化や人が大きく損なわれれば継続自体が難しくなる可能性さえ感じていました。一方で、活動をやめれば支援や再生の手助けもできなくなる。私たちが一助になるためにやめる選択はできず、「どう続けていくか」「何ができるか」を真剣に考え続けました。
当時はちょうどお正月で、メンバーの多くは帰省で珠洲を離れていましたが、すぐにでも現地に戻りたがったため、会社として「今はまだ入らないように」と制止する必要があったほどでした。それくらい全員が珠洲という地域に深く入り込み、自分ごととして向き合っていたのだと強く実感しました。

「廃業」を口にされるパートナーもいらっしゃった状況から、再起へと踏み出されていく過程で、地域の事業者の方々とはどのような連携をされたのでしょうか。
震災直後、現地の社員やスタッフは自主的に避難所の支援や現地活動に関わっていましたが、事業者の皆さんの生活そのものがままならない状況だったため、具体的な連携はほとんど取れていませんでした。
幸い、連携していたパートナーの多くは今も前向きに活動を続けています。被害の大きさによっては困難な状況のところもありますが、私たちの周辺では元気に動き出している方々も多く、地域の底力を感じています。
会社としては、今回の経験から「地域共同体」としてのつながりを強化する必要性を痛感しました。企業にはBCP(事業継続計画)がありますが、地域内の多様な組織が連携する仕組みは十分な整備がされていないと感じたのです。
企業として初動でどこまで踏み込むべきか、支援が逆に迷惑にならないかという判断には迷いもありましたが、これからは地域企業としての立場を明確にして、有事の際にも共同体の中で機能できる存在でありたいと思います。
災害は日本中どこでも起きるものなので、地域住民も含めたネットワークを最大限に活用した取り組みが他地域にも横展開されていくことを願っています。
ユーザーに声を届けてもらいながら深化させていくプロダクト

2024年5月、ようやくリリースできた時のお気持ちを教えてください。
2024年1月の能登半島地震からわずか4カ月でリリースにこぎつけられたことは、今振り返っても奇跡的でした。現地の協力者やチームメンバーが力強く支えてくれたおかげだと思います。
リリースの準備は長く進めていましたが、震災を経て一度立ち止まったことで、自分たちが何のためにこの製品を届けるのか、誰のために動いているのかを改めて深く考える時間になりました。
結果としてクラウドファンディングや販路拡大といった新たな動きにつながり、震災がプロジェクトの方向性を明確にする一つの転機となったように思います。

まさにこの4月1日にはブランドをリニューアルされて、新生NAIAとしてのスタート地点になるかと思います。ユーザーの皆さんへ伝えたいことはありますか?
2025年4月1日、「NAIA」のブランドリニューアルを実施し、新たなスタートを切りました。製品面・ブランド面ともに刷新し、これからの在り方を再定義するタイミングになったと実感しています。
私たちは珠洲市内の農家から米を直接仕入れ、自社で育てて、工場で酒かすなどの副産物から健康成分・美容成分を抽出しています。スキンケア業界でも珍しいこのアプローチは、能登の価値を可視化することにつながっています。
まさに私たちが大切にしてきた「土地と共にあるブランド」という姿勢を体現したもので、多くの方にその意義を知っていただきたいです。
そして、何よりも大切にしているのは「ユーザーとの対話」です。
商品を手に取ってくださる方々には、良かった点はもちろん、「こうした方がいい」「ここは使いにくかった」など、率直なご意見をいただけるとうれしいです。
そういったフィードバックこそが、NAIAをさらに良いものにしていく原動力になります。これからも皆さんと一緒に、ブランドを育てていく姿勢で歩んでいきたいと思っています。
本日はありがとうございました。