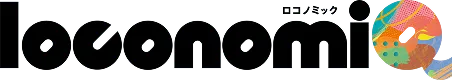株式会社NAIA 代表の清水 雅楽乃さんに、「自分らしさを表現できる場所で取材をさせてください」とお願いすると、約1万5千坪の広大な土地で、引退した競走馬たちが伸び伸びと暮らす施設へと案内いただいた。
「能登のものづくりも東京の競争社会も、どちらも純粋で私にとっては両方必要」と語る清水さん。「人と馬が共生する森の放牧場」として誕生した珠洲ホースパークを舞台に、清水さんの生い立ちや将来像、ローカルな土地に住む人たちへの思いを伺った。

1984年北海道札幌市生まれ。2007年に株式会社オプトへ入社し、ソウルドアウト創業に参画。営業領域の責任者として全国の中小・ベンチャー企業支援を拡大し、ソウルドアウトの東証マザーズおよび東証一部上場に貢献。その後、CROやマーケティングカンパニープレジデントを歴任し、2024年より専務取締役COOに就任。
現在は「ローカル×AIファースト」戦略のもと、全国拠点展開とデジタル活用を通じて地域企業の成長を後押しし、日本経済の持続的な活性化に取り組む。

目次
まぶしいほど太陽が差し込む珠洲ホースパークとの出会い

清水さんらしさについてお話を伺う場として、この珠洲ホースパークを選ばれた理由を教えてください。
日差しがたっぷりでとにかく明るく、馬が本当にかわいい。敷地内のクラブハウスのような建物もおしゃれで好きな場所なんです。
初めて訪れた頃はまだ構想段階で、調教師の角居さんから「こういう場所をつくりたい」という話を聞いていました。代表を務めている足袋抜さんとも相談し、資金の話が出たタイミングで私たちのファンドをご紹介したのがきっかけでした。
震災で全壊した本社はこのホースパークから徒歩数分の距離です。現在販売している「ラフマ」というハーブを育てていたこともあって、このあたり一帯が私たちの事業や暮らしと深くつながっている場所なんです。
だからこそ、ここにいると自然と気持ちが落ち着きます。訪れる人にもそう感じてもらえるんじゃないかと思います。
今後はもっと手を加えて、観光コンテンツとしても人が集まる場所にしていきたい。地域を盛り上げる場として、ここを育てていきたいですね。
苦労の絶えない母の姿を見て芽生えた自立心

そんな特別な場所でお伺いしたいと思いますが、清水さんの幼少期はどのような様子だったのでしょうか?
幼稚園に入る前までは、両親のほかに父方の祖母とその姉、さらに曽祖母も一緒に暮らし、大人がたくさんいる家でした。嫁姑、姑の姉や母など女性ばかりの空間でよく言い合いがあり、毎日がにぎやかで、なかなかハードでしたね。
母がよく涙する姿を見て、家庭内の空気を子どもながらに感じ取り、「自分がなんとかしなきゃ」といつも思っていました。1つ年下の妹もいたため、姉としての使命感のようなものを感じていたのかもしれません。
しばらくして家族4人で引っ越しましたが、その後もともと住んでいた家に戻り、新たに家を建て直して、結局また二世帯生活に戻りました。
上京はいつ頃だったのですか?また、その時の心境を教えてください。
高校までは大阪の箕面市で過ごしました。大学進学を機に上京したのですが、家庭に対して“しがらみ”を感じていた当時は「大人から解放された」という気持ちがすごく大きかったです。
家庭では教育も厳しかったです。父は医師で、母は専業主婦でしたが、結婚前は教師をしており、まさに「教育者的な母親」でした。祖母も母に対して「勉強ができる子にしっかり育てるべき」というプレッシャーをかけていたようで、母自身も私を“きちんと育てなければ”という思いが強かったのだと思います。
私はあまり素直な子どもではなかったですし、成績は期待値以下だったので、母とはよくぶつかっていました。習い事もたくさんあり、ピアノ、バレエ、お習字、英会話、囲碁など、ほぼ毎日予定が詰まっていて、正直オーバースケジュールでした。でもなんでもがんばりました。
成績は1番ではなかったですが、悪くもないですし、ピアノは毎日練習してお教室ではかなり上手なほうでした。バレエはとても下手でしたが週2回通っていました。さらに、「期待に応えなきゃ」というプレッシャーも常に感じていて、気の休まる時間がなかなかありませんでした。
だから東京に出たとき、「やっと自由になれた」という気持ちがあって。その解放感が大きかった分、進学というより“自立”に近い感覚だったかもしれません。
清水さんと妹さんは現在も連絡を取り合っているのですか?
妹に対しては、一緒にあの環境を生きてきた同志のような思いがあります。
彼女は三重県松阪市の飯高という地域で家族と暮らしていて、15年ほど前からほぼ自給自足の生活を続けています。子供は4人もいます。実はメディアにも何度か取り上げられているんですよ。
電気や水道は通っていますが、それ以外はほぼ全てを自力で賄っています。裏山でわなを仕掛けて獣を取ったり、野菜を育てたり、ウコッケイを飼って卵を取ったり。本当に生活そのものを自分たちの手でつくっている感じです。
当時は「なんて極端な暮らし方なんだろう」と思っていましたが、今の私の仕事も自然の素材を扱い、地域に根ざしたものづくりをしています。自然と近い場所で生きているという点では、むしろ今の方が妹に近づいているような感覚があるんです。
昔は正反対の生き方だと思っていましたが、気づけばどこか通じ合うものがあります。それぞれ違う道を選んだように見えて、今では似たような価値観を共有しているのかもしれませんね。

学生時代なども含めて、現在につながる経験や思い出などがあれば教えてください。
子どもの頃から「ノーと言わずに頑張る」というのが、自然と染みついていたように思います。
大学時代はその反動が少し出て、前半の2年間はサークルに没頭し、3年生の終わり頃には公認会計士を目指して勉強に打ち込んでいました。でも結果は不合格。もう一回チャレンジしたかったのですが、親から「留年は許さない」と言われ、大学4年の夏以降に就職活動へ切り替えなくてはいけませんでした。
その頃には一般的な新卒採用が終わっていたのですが、アクセンチュアというコンサルティング会社が一つ下の学年の皆と一緒に採用試験を受けることを許諾してくれて、大学4年生の秋に受験して12月に合格し、4か月後の4月に入社した格好です。
親からはなんとしても留年するな、と言われていたものの一般的な入社の窓口は閉まっている中どうしたらいいのか悩んでいたので、その自由な雰囲気に救われた部分も大きいですね。友人たちもびっくりしていましたが、滑り込みセーフというやつでした。
思えば、就職活動というのは自分が何をしたいのかを熟考すべき期間だったとも思いますが、当時は職業選びよりも「ちゃんと自立して生活できるようになりたい」という思いが強かった当時の私にとっては、本当にうれしかったです。

会社を辞めようと思ったきっかけは何だったのですか?
ただ、結婚を機に、その会社を辞めました。当時はとにかく多忙で夜中まで毎日のように働き、プライベートとのバランスを取るのが難しくなっていたんです。また親からより一層の自立を進めるために自分の家庭を築きたいという思いも強く、あっさりと辞めてしまいました。正直、少し後悔しています。
小さなM&Aの会社に転職し、大学時代に勉強した会計の知識を生かし財務コンサルティングの仕事をしていましたが、だんだん飽きてしまいました。結局もう少し大きな会社で働きたいと思って別のコンサル会社に転職しました。
こうして振り返ると20代は自分がどこに向かいたいのか、はっきり見えていない時期でした。頑張ってはいたものの「何のためにやっているのか」という答えは見つからないまま。自立したい思いや自分の場所を築きたいという悩みはあるものの、自分のやりたいこととしっかりと向き合えていなかった。
当時は、自分の意思で未来を描けず、30代前半までは「やり切れていないな」という気持ちがどこかにありましたね。とはいえ、当時の激務で得た経験やスキルが、今の自分につながっているのは間違いありません。コンサルティング会社で培ったものは私の誇るべき大きな財産で、これまで働かせてくれた会社にはとても感謝しています。
能登の純粋なものづくりも東京の競争社会も、私にとってどちらも必要

実際にローカルというものに触れて、東京だけで働いていたら得られなかったと感じる瞬間はありましたか?
改めて実感したのは「東京もローカルも、どちらにも純粋さがある」ということです。東京には、競争の中でいいものを目指していくストイックさがあり、珠洲には自然や職人技に対する真っ直ぐなまなざしがある。
まったく違うけれど、どちらも誠実で、両方に心地よさを感じています。東京にいた頃は、正直「地方創生」とか「ローカルの価値」というものがあまりよくわかっていませんでした。どちらかというと、中央にものを集約して効率を高める方がいいのではないか?と考えていたくらいです。
でも実際にローカルの営みに触れてみると、その考えがいかに偏っていたかに気づかされました。中央で植物工場を整備して酒蔵や水田も全部まとめてしまえば効率的かもしれませんが、それはもう“日本じゃない何か”になってしまう気がしたんです。
やはり文化や方言、土地ごとの暮らしがあってこそ「日本」なのだと感じましたし、そのバランスの中でこそ、新しい価値が生まれていくのかもしれませんね。

現在の清水さんにとって、能登地方や珠洲市はどのような存在になりましたか?
能登や珠洲は私にとって、自分自身を深く見つめ直せる特別な場所になりました。あまり意識してこなかった「生きざま」のようなものを、初めて考えさせられた気がします。小さい頃から、両親の期待に応えることを前提に生きてきましたが、そのことにずっと強い違和感を持っていました。とはいえ、その違和感に明確な言葉を与えることができず、子供ですし、主張が通るわけでもない。だから、ただ反発するのではなく、「結果を出すこと」で自分の意志を守ろうとしていたように思います。
コントロールされないために、努力して成果を出す――そんなふうに、自立を模索し続けてきたのかもしれません。
東京にいた頃は自分に向き合う機会をなかなか持てませんでしたが、ここに来てからは自然と立ち止まるようになりました。この土地の空気や暮らし、人との距離感が、そういう時間を与えてくれたのでしょう。
不思議なことに、芸術家の方や創作活動をしている人が集まってくるのもこの場所の特徴です。何か「内面に向き合う力」を引き出してくれる土地なのだと思います。
このエリアに住む地域の方々を見て、どのような印象を持たれましたか?
地域の方々を見ていると、皆さん本当に自立されているなと感じます。「これがない」「あれが欲しい」といった言葉をほとんど耳にしないんです。
物理的には「何もない」と思われがちな場所かもしれません。
でも実際には、自然と共生しながら、人の手で美しい風景や文化をつくり上げてきた豊かさがある。自然に寄り添いながら暮らすこの土地の人たちは、東京とは違う強さを持っていると思いますね。
そして何より、地域の人たちにとって「当たり前」になっている町並みや伝統工芸、暮らしの美しさを、私たちも一緒に持続可能な形で次世代に引き継いでいきたいと考えています。
文化や風景を廃れさせずに続けていくことは、私たちの世代の義務なのかもしれませんね。
今回の震災では、能登から多くの風景が失われてしまいました。これからまた新しいものが建てられていくと思いますが、それがどんな形になっていくのか、まだ見えていません。
ただ、能登には能登なりの復興のあり方があるような気がしています。理想を言えば、デザインや文化を意識した町づくりができたらいいのですが、誰がそれをリードしていくのかというと、簡単な話ではありませんね。
ただ新しくするだけではなく、残すべきものは何かを丁寧に考えながら、次の時代をつくっていけたらと思っています。
自分に正直になれたのは、珠洲で新規事業を始めたから

プライベートの自分と経営者としての自分の間に、ギャップを感じることはありますか?
本来の私は、どちらかというと「型にはまった思考」で物事を整理するタイプでした。ある種の起業家のように情熱一本で突き進むのではなく、合理性や効率を重視して、中央から物事をコントロールする方が正しいと信じてきたんです。
でもそれが変わったのは、珠洲で新しいチャレンジを始めたからこそなんです。
ここで出会った人たちは、数字では割り切れない価値観の中で生きていて、暮らしやものづくりに真摯に向き合っています。そういう人たちと一緒に何かをつくろうとすると、会社の論理だけでは立ち行かない。むしろ、自分自身のままで誠実に向き合うことの方が大切なんだと気づかされました。
そう考えると、今では「経営者の私」と「個人としての私」の間に、大きなギャップは感じていません。むしろ、ここでの経験が、私自身の価値観そのものを少しずつ変えてくれたのだと思います。
これまでの経験を通して、ご自身の成長を実感することはありますか?
正直なところ、昔は社会で生き抜くために、自分を守るためのよろいをいくつもまとっていました。それがないと不安で仕方なかったんです。
でも今は、それを脱げるようになってきた気がします。「ちゃんとしなきゃ」「結果を出さなきゃ」といったプレッシャーも、自分を奮い立たせる大事な力でしたが、今振り返るとそれが重荷になっていた部分もあったなと思います。
とはいえ、資本主義のど真ん中に居たからこそ、実力を出せば誰でもチャンスをつかめるピュアな世界観にも触れられました。それはそれで素晴らしい経験だったと感じています。都会で培った経験も、今この場所で育っている感覚も、どちらも大切にしたい成長の糧ですね。
毎日の原動力は「明日は今日より幸せだ」と思える心

経営者というよりも一人の人間として、これからのキャリアにどのような姿を描いていますか?
組織がなくても生きていける人間になりたいという思いがあります。
珠洲では職人さん達をはじめとした「組織に属さないで生きている人たち」と関わる機会が多く、そういう人たちを見ていると本当に強いなと感じるんです。何があっても自分の足で立ち、場所にもとらわれず働いている。その在り方にすごく憧れますね。
一方で自分はというと、どこへ行っても「これが自分の仕事です」と言えるような手に職がついた状態にはなっていない。だからこそ「私はこれができる」と胸を張って言えるような力を身につけて、どこでも働ける自分になりたいと思っているんです。
「絶対にこれはやってみたいな」という事はありますか。
専門性や経験は積んできましたが、それでも「組織に頼らずとも価値を発揮できる人間でありたい」という想いがあります。
それは、独立を志しているという意味ではなく、どんな場所にいても自分の足で立ち、自信を持って判断し、人を動かせるような人間でありたい、ということです。
珠洲では、職人さんや個人で生計を立てている方々と関わる中で、「個としての強さ」を持った人の在り方に強く惹かれました。組織に属していないから強いのではなく、自分の中に確かな拠り所や軸を持っているからこそ、誰かの力にもなれる。そんな姿に学ぶところが大きかったんです。
私自身も、会社という場で多くの人と関わりながら物事を動かしていく立場にあります。だからこそ、環境や肩書に依存せず、自分という人間の中に“推進力”を宿しておくことが、これから先のキャリアでより重要になると感じています。
組織に属しながらも、組織に依存せず、むしろ自立した個としての強さで、チームや地域を前向きに巻き込んでいけるような存在を目指していきたい。そんな思いを持っています。
いま、バイタリティーを持って頑張れている原動力って何になるんですか。
たぶん私は、ポジティブな性格なんだと思います。
子どもの頃は、大人の家族の誰かしらが泣いている場面が多くて。だからといって「嫌だ」と感じたわけではなく「なんでそんなに泣くのかな」「泣くくらいなら行動したらいいのに」と、ただ不思議に思っていました。もしかすると、それが「私はもっと明るくいよう」と思うきっかけになったのかもしれません。
モチベーションが下がることもあまりなくて、「今日より明日の方が楽しいはず」って自然と思えるんです。だって、生まれた瞬間って知識もなければ喋ることもできない。ある意味いちばんしんどいじゃないですか。それが日々少しずつアップデートされていくと考えれば、明日の自分は今より当然幸せだって思えるんです。
「代表取締役だからこうでなければ」とかも、重く考えすぎないようにしています。先のことも、あまり考えすぎないようにしていて。10年先のことを計画するより、目の前のことをちゃんとやっていく方が、自分には合っていると思っています。
本日はありがとうございました。